銀行業務検定の中でもメジャーな法務、税務、財務。
初めて試験にチャレンジしようと思っているあなたは、どれから受ければいいかわからなくていつまでも受験申込ができないのではありませんか?
もしくは、受験してみたけど合格できない…諦めて他の試験にチャレンジしてみようかな? なんて考えていませんか。
実は、受験する順番や時期をしっかり計画することが合格への近道です。
この記事では、実際に受験して一発合格したわたしが「これがベスト!」という受験する順番を解説します。
この記事を読めば、効率よく銀行業務検定を合格できますよ。
はじめに:銀行業務検定ってなに?
銀行業務検定とは…
「主として銀行・保険・証券等金融機関の行職員を対象に、業務の遂行に必要な実務知識および技能応用力についてその習得程度を測定することを目的に、さらには実務納涼水準の向上に寄与することを願って1968年2月からスタートした公開の検定試験です。
銀行業務検定協会ホームページより引用
今では23系統36種目の試験を実施している銀行業務検定の中でもメジャーなのが「法務」「税務」「財務」です。
国家試験のFPや宅建は、スマホで調べれば学習方法や過去問などの情報が多くあります。
この銀行業務検定はホームページ上でも問題が公開されておらず、参考書や問題集なども一般の書店では手に入らないマイナー試験です。
どんな人が受験するの?
銀行業務検定を受験をする人のほとんどは現役で金融機関に勤めている人です。
大手の金融機関によってはキャリアアップの条件にもなっています。
金融機関の職員の必須資格「証券外務員試験」とは違い、持っていないと何かが販売できないとか営業できないといったことはありません。
しかしながら、銀行業務検定の受験を推奨している金融機関は多いです。
多くの受験者は働きながら試験に向かって勉強することになります。
限られた時間でいかに効率よく学習していくかが重要です。
初めてチャレンジするなら、やはり難易度が低い試験からの受験がおすすめです。
.png)
わたしが受験した順番をお教えします。
- 財務3級(2017年3月)
- 法務3級(2017年6月)
- 税務3級(2017年10月)
.png)
どれも一発合格ですよ!
最初は知識がなかったため、とりあえず日商簿記2級を持っているからという理由で財務を選びました。
法務3級は年2回しか試験がなかったのでこの順番になった…計画性はありません。
実際に受験したみた経験から、やっぱり受験する順番はしっかりと考えた方がいいです。
それぞれの難易度は? 受験してみて感じること
銀行業務検定の3級はマークシート方式です。
100点満点中60点正解で合格です。
間違えないで欲しいのが、100点を目指す必要はないということ。
あくまで60点で合格できますから確実に得点できる問題を攻略することが合格への鍵です。
実際にわたしの経歴を紹介します。
預貯金等もやりながら保険分野の担当として金融機関の窓口業務を10年近くやっていました。融資はほとんどやってません。
学生時代は商業系の学校だったため、簿記や社会人になってチャレンジした資格試験は、証券外務員試験、損害保険募集人、FP3級、FP2級です。
法務3級の難易度
「税務」「財務」「法務」で一番難しい試験はどれでしょうか。
「法務」では手形や小切手の法律上の効力や民法の解釈など幅広い知識が問われます。
その中でも「融資」がらみの法律(主に民法)が難しく、過去問を何度やっても答えを迷うほどでした。
出題される問題も「絶対に」「当然に」「例外なく」など、ひっかけのような問題文ばかり。
裏読みしすぎて不正解を選んでしまうこともしばしば…。
.png)
なんとか合格できたけど、
ラッキーだったとしか言いようがありません。
試験問題は読解力が必要で、問題を理解できないと正解ができません。
ていねいに進めすぎると最後の問題までたどり着けない時間切れの可能性もあります。
法学部卒業の人、宅建取得済の人、民法の知識がある人は難易度がグッと下がります。
法律関係が得意な人は法務からの受験もあり!
わたしが受験したころは、分野ごとの足切り点がありましたが、今はないようなので難易度は下がったように思います。
足切り点は「全体で60点で合格点に達しても、分野ごとに最低正解数を上回らないと合格にならない」ような仕組みのこと。
足切り点があると「不得意分野は捨てて得意分野で得点する」ような学習だと不合格になってしまうのです。
わたしが使った問題集や参考書はこちらの2つ!
税務3級の難易度
銀行業務検定の「税務」の難易度は「財務」「法務」にくらべて低めです。
「税務」は問題集のみの学習で90点台を獲得できるほどシンプルに学習しやすい試験でした。
税務はFPのタックスプランニングなどで勉強したため.なじみのある分野で学習を進めやすかったのもあります。銀行業務検定「税務」の問題の一部は法務で勉強したことも役に立ちました。
通常の確定申告の知識だけでなく、相続税や譲渡所得の計算問題なども出題されますが、しっかりと計算式を暗記すれば難しい問題ではありません。
.png)
税務は参考書を買わなくてもスマホで調べれば十分です。
国税庁のホームページから確定申告の手引きをダウンロードするのがおすすめ!
税務は、過去問解説集のみの学習で十分合格できます。
わたしは実際に、理解が必要と思う項目については国税庁のホームページなどを活用して調べて学習を進めていました。
意外と法令等に則って問題が作られているため、学習を進めやすかったです。
受験者の中には「税務」が一番難しいという人もいます。
税法は毎年のように変わるので、今年勉強したことが来年は役に立たないことがよくあります。
したがって問題集や参考書は最新のものを使わないといけないし、受験する時期を決めてから学習しないと効率が悪いのです。
「税務を受けるつもりで勉強していたけど、仕事忙しくなったから来年に延期しよう」と計画を変更する可能性がある人は注意です。
銀行業務検定の税務3級であれば、受験を申込してから学習を始めれば十分間に合います。しっかり勉強すれば合格できますので、思い切って受験申込してしまいましょう!!
財務3級の難易度
「財務」は会計(貸借対照表や損益計算書作成)の知識や経営分析の知識が問われる問題です。
過去に出題された問題の焼き直しがよく出るので過去問中心に的を絞って学習すれば合格できます。
会計はよくわからなくても暗記が得意な人は勘定科目や計算式を丸暗記しておけば高得点が狙えます。
法務のように日本語が難しくて迷うような問題は出ません。
問題集のみでの合格も可能ですが、知識を深めたい人は参考書の購入がおすすめ!
会計の基本的な知識や計算式は変わることがないので過去に受験した人が身近にいれば問題集や参考書を譲ってもらいましょう。
たとえ5年前の参考書だったとしても税金の計算が変わることはあっても会計の原則が変わることはありません。
安く購入できるのであれば中古品も検討していいかもしれません。
心配であれば問題集のみ最新のものを用意します。
受験者の中には銀行業務の仕事に活かすことを考えて財務3級にチャレンジする人もいると思います。
しかしながら、業務に活かすための勉強であれば日商簿記3級程度の知識だけで充分です。
もし、簿記検定か銀検の財務かと言われれば簿記検定を受験したほうがいいです。転職や再就職などにも簿記資格は有利です。
「財務」は、あとから受験した「税務」の試験にも出る知識が一部ありました。
おすすめの受験の順番は?
もしわたしがもう一度受験するのであれば、
「税務」→「財務」→「法務」で受験したいと思います。
「税務」は過去問を何度かやれば合格圏内に入れるので、仕事をしながら勉強をする習慣をつけるにはもってこいです。
最初はモチベーションが上がらないかもしれませんが、合格してはずみをつければ次の試験もやる気が出るはずです。
「税務」の次は「法務」でも「財務」でもどちらでも好きな方を受験してかまいません。
わたしが実際に受験して、一番難しいと感じたのが「法務」でした。
そのため、学習のスケジュールを確立できる最後に受験したいと思いました。
資格試験の勉強は毎日の習慣にすることが合格への近道です。
仕事をしながら勉強する時間を作るのはなかなか大変です。
自分なりの勉強方法を確立していきましょう。
合格のポイント
最後に:勉強を習慣化して合格を目指そう!
仕事で疲れてるのに勉強するなんてとてもできないと考えているあなた。
分かります、わたしもそうでした。
そんなわたしも職場で必然的に受験しなければならなくなり、どうせやるなら効率よく! をモットーに一発合格を目指し頑張りました。
効率の悪い学習方法だったとしても、あと一歩のところで不合格になればまた最初から勉強しないといけない。
それだけは避けようと仕事や育児の合間を縫ってなんとか勉強をする時間を確保してきました。
受験当時、わたしが考えていたのは一発合格することだけでした。
それが一番効率がよいと思ったからです。
今振り返るともっと効率よくできたと思います。
受験する順番を決めること、100点を目指さずに合格すること。
そんな反省もあって、この記事を読んでくださったあなたにはもっと効率よく合格を目指してほしいと思っています。
あなたのヒントになればわたしもうれしいです。
この記事もおすすめ!
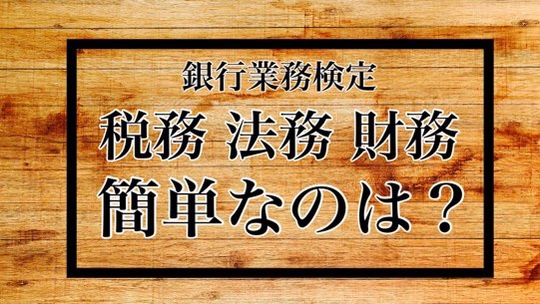
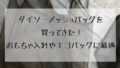
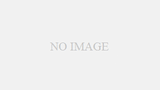
コメント
[…] →銀行業務検定を受験する順番についてはこちらの記事参照 […]